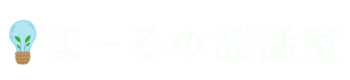セルフ・エフィカシー(自己効力感)とは
「セルフ・エフィカシー」は、カナダの心理学者アルバート・バンデューラ氏が提唱した社会的学習理論。「自己効力感」と翻訳されます。
ちなみに
バンデューラ氏は世界で4番目に多く引用されている心理学者(2002年調査)で、2015年にはアメリカ国家科学賞を受賞するなど、その学問的功績が高く評価されています。2021年7月に96歳で逝去されました。

bandura@stanford.edu - Albert Bandura, CC 表示-継承 4.0, リンク
セルフ・エフィカシーとは、「ある結果を生み出すために必要な行動を、どの程度うまくできるかという個人の確信」のこと。
簡単に言うと「自分はやれるんだ、という自信」のことです。
実はこのセルフ・エフィカシーが、メンタル疾患の克服に大きく影響していることが分かっています。
パニック障害においては、①パニック発作に対する極端な自動思考・スキーマ(「大変なことが起きる!」「死んでしまうかも!」など)を改善することと、②「自分にはパニック発作に対処する力がある」というセルフ・エフィカシーを向上させることがとても大事です。
とりわけ「不安感を下げる」という点に対しては、②セルフ・エフィカシーを向上させることが直接的な影響を与えるという研究結果があります。(*参考:熊野)
「自分はパニック発作に対処できるんだ!」という自信を高めることは、パニック障害の回復にとって無くてはならない要素だということです。
セルフ・エフィカシーを高めよう
セルフ・エフィカシーは自然と高まるのではありません。以下の方法によって、自分で作り上げていく必要があります。

セルフ・エフィカシーの手に入れ方
- 自分で実際にやってみて、成功体験を積む(達成経験)
- 誰かの成功体験を知る(代理経験)
- 「自分にもできる」と自分を励ます/誰かに励ましてもらう(言語的説得)
- 身体の健康を保つ(生理的情緒的高揚)
成功体験を積む
これは、エクスポージャーの実践によって得られるところが大きいでしょう。
不安階層表を作ってエクスポージャーを段階的に実践し、自動思考やスキーマにもアプローチをかけていくことです。
目標が達成できたときには、手放しで自分を褒めること。
それが成功体験を積む上で、一番大切。
-

-
参考エクスポージャー(曝露療法)
続きを見る
誰かの成功体験を知る
実際にパニック障害や不安障害を克服した人をロールモデルにすることです。
「治った人がいる」その事実だけで、少なからず勇気がもらえるのじゃないでしょうか。
そして、「治った人がいるなら自分にもできる」という自信にも繋がるでしょう。(筆者もロールモデルになれればと願っています。)
これは避けよう
逆に「治らない」というキーワードでネット検索をしたり、「まだ治っていない」人をロールモデルにするのは避けましょう。
自信を失わせるような行為は、回復の妨げになってしまいます。
自分を励ます/誰かに励ましてもらう
「自分にもできる!」そうやって自分を励ますのは、パニック障害・不安障害のときにはなかなか難しいかもしれませんね。
だからこそ、その根拠を得るために成功体験を積んだり、成功した人をお手本にしたりするという話をしたばかりです。
だけどそうやって成功体験を積み重ね、成功体験をした人に勇気をもらいながら治療を進めていくと、「自分にもできる!」と自分を励ますことは案外スムーズにできるようになってくるものです。
それまでは、誰か周りの人に「あなたならできるよ」と励ましてもらうのも効果的でしょう。
これは避けよう
「君にできるはずがない」「そんなことやって何になるの?」そんなふうに自分の足を引っ張るようなことを言ってくる人からは、今は少し距離を置きましょう。
もしも距離を置けないようなら、それよりもっとたくさんの励ましの言葉が得られる環境づくりを。その点ではツイッターなどで同志と励まし合うのも効果があるかもしれませんね。
身体の健康を保つ
古代ローマに「健全なる精神は健全なる身体に宿る」という格言があるとおり、身体の健康はそのまま心の健康に影響を与えます。
でもこれは「体調不良を抱えていることが絶対的にいけない」ということではありません。体調不良は誰にだってあることですから。
大切なのは、自分なりに今できる精一杯の健康管理を心がけるということです。
散歩をして体力をキープしたり、寝る前にPCやスマホを見ない習慣をつけたり。バランスの良い食事をとることも大事ですよね。
呼吸法や腹式呼吸を生活に取り入れて、普段からリラックスを心がけるのも大切なことです。
健康を心がける上で、決してムリをしすぎないことも忘れてはいけませんね。
自信を失う行為をやめよう
「自信をつければ、不安は下がる」
こうして文字にしてみると、ずいぶん当たり前のことのように映りますね。そう、実は知識としては基礎的でシンプルなことでもあります。
学生の頃にクラブ活動なんかをしていた人は、感覚的にしっくりくるのじゃないでしょうか。
試合やコンクールで良い結果が出せるだろうか。その不安を打ち消すために、たくさん練習をして自信をつけたという思い出があるのではないですか?
また「自信」というのは「自分を信頼する」というふうに書きますよね。言い得て妙です。
そういう意味では「自分を信頼する行為」とちぐはぐな行為、つまり「自分を信頼していない行為」を少しずつやめていくことも大事なことです。
「その行為に何が当てはまるのか」「そういう行為を自分はしていないか」ということに注目してみるのも、セルフ・エフィカシーを高める上で欠かせない作業になるでしょう。
自信を失う行為の一つでもある「回避行動」や「安全行動」については、また別の記事でご紹介します。
-

-
参考安全行動を気持ちよく卒業するには
続きを見る
自信を取り戻しましょう。今は「自分の対処能力を過小評価しているだけ」に過ぎませんから。