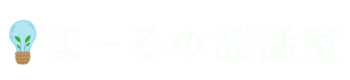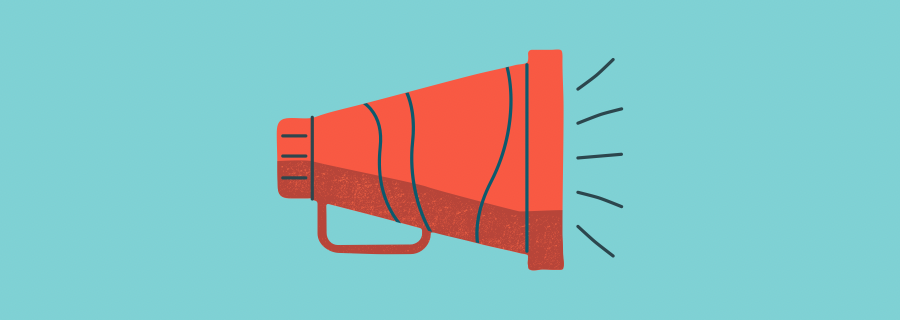セルフ・エフィカシーを高めるために
セルフ・エフィカシー(自己効力感)を高めるためには、実際に成功体験を積んでいくことの他に、誰かの成功体験を見聞きして勇気をもらうことや、誰かに励ましてもらうことなども効果的だと言われています。
-

-
参考セルフ・エフィカシーを高めよう
続きを見る
そういう意味では「治し方」を具体的に教えてもらうというのもまた、勇気や自信を得られるという点でオススメです。
ひとつ、うってつけのYouTubeチャンネルがありますのでご紹介しますね。
心療内科の先生のお話を聞いてみよう
「新宿オーピー廣瀬クリニック」の公式YouTubeチャンネルです。
心療内科・精神科の臨床医である廣瀬氏が、パニック障害を含むさまざまなメンタル疾患の「治し方」のヒントをくれるチャンネル。
リワーク(職場復帰に向けたリハビリ)プログラムやグループ療法の記録動画だとのことです。
80本ほど(2021年時点)の動画が公開されています。ちょっといくつか見てみましょう。
参考動画① メンタル治療の3つのポイント(自己努力・忍耐・薬物療法)
20分弱の動画ですが、さすがに内容が濃いですね。ざっと抜き出してみます。
![]()
- メンタルは「放っておいて自然に治る」部分が比較的少ない
- お薬はあくまで一時しのぎ(先生いわく「補助剤」)なので、お薬だけに頼らないのが大事
- 長期的なストレスで脳の神経細胞がダメージを受けている場合は、薬や自己努力が功を奏するまで「回復を待つ」必要がある
- 待つのは案外難しい
- 十分待つと、コロッと変化が訪れる(薬の効果が出てきたり、自己努力ができるようになってくる)
- すべてのメンタル疾患の回復には自己努力が不可欠
回復に時間がかかるのは大前提なので、「周りがとやかく言わない」のも大切なことですよね。
そういう意味では、疾患に理解のない人との距離感を見極めるのも重要になるでしょう。
参考動画② 自分の感情処理 - 言語化
自動思考とスキーマの概念に通じるものがありますね。
![]()
- 感情や状況を「言語化」することで、気持ちに整理がついて落ち着くことができる
- 言語化のステップは①「状況を言葉にする」②「感情を言葉にする」③「解釈と対策」
- 感情的な人に囲まれて育った人は、状況を説明するのが苦手
- 真面目ながんばり屋さんは、自分の感情に気づくのが苦手
- 状況に対して客観的な解釈を与えて、対応・対策を考えるのが大事
「今日はこんなことがあった(状況)」そして「それに対してこんなことを思った(感情)」を書き出すことが、言語化の練習になるそうです。
つまり日記ですよね。言語化が苦手な人は日記を書く習慣をつけるのがよさそうです。
参考動画③ 定刻に起床する意味について
「早起きがいい」というのはよく言われることですが、むしろ決まった時間に起きるというのがポイントなのですね。
![]()
- 定刻に起床すると思考の切り替え(ON/OFF)がうまくなる
- 思考の切り替えがうまくなると、ネガティブ思考が延々と続くようなことも減る
- 思考の切り替えが苦手だと、ついダラダラしてしまい行動がスムーズにいかなくなる
- 昼夜逆転の生活になってしまった人は、まず決まった時間に起きる練習から(スヌーズ機能に頼らない)
規則的な生活習慣をキープすることは、ネガティブ思考の切り替えにも効果があるんですね。目から鱗です。
服薬そのものに不安を感じている人へ
その他にも減薬について、復職について、不登校についてなど、さまざまな動画を公開されておられます。
さすが臨床の先生のお話だけあって、「なるほどそうか」と納得できる内容ばかりです。
基本的には自己努力を重要視されていますが、医師の立場から服薬の大切さも等しく語られています。(お薬を必ず服用しなくてはいけないという言及はありません。)
「薬を飲まない」のではなく「薬だけに頼らない」のが回復のカギ。
そして最終的には薬からの卒業を目指し、症状の回復とともにゆっくりと減薬していくのがいいとおっしゃっています。
精神科のお薬を飲むことそのものに不安を感じておられる場合には、廣瀬先生の動画が勇気をくれるかもしれません。
「自己努力ってどうすればいいの?」というヒントも得られるかと思いますので、よろしければ参考にしてみてください。