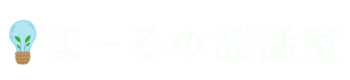ネガティブ思考の元になる考え方
何か出来事が起こったとき、反射的にわき起こる思考を「自動思考」と言います。
そして、その自動思考に影響を与えているのが、「スキーマ(信念)」です。
-

-
参考自動思考とスキーマ(信念)
続きを見る
人によって抱えているスキーマは異なりますから、当然自動思考にも個性が出てきます。
例えば、仲の良いお友だちにLINEを送ったとします。すぐに「既読」がついたのだけど、なかなか返事が返ってきません。
このとき「ああ、忙しいのかもしれないな」と思う人もいれば、「ムシされた! ひどい!」と思う人もいます。
このように、同じ出来事への反応が人によって異なるのは、それぞれ抱いているスキーマが異なるからなのです。
後者の人は、ずいぶんネガティブな反応をしていますね。
ネガティブな自動思考には、多くの場合その裏側に極端に凝り固まった考え方が隠れています。
ここにその代表的なスキーマを7つ挙げてみましょう。
![]()
マイナス思考
良いことを無視して、何でも悪い意味にすり替えてしまう。
![]()
拡大解釈・過小評価
自分が気にしていることや自分の短所などを大げさに捉え、自分の考えに合わないことや自分の長所などを過小評価する。
![]()
感情的な決めつけ
その時の自分の感情に基づいて、現実を判断してしまう。
![]()
「すべき」思考
何事も「〜すべき」「〜すべきでない」というふうに考えて、行動を制限してしまう。
![]()
一般化し過ぎ
少し良くないことがあると、「いつもこうだ」「うまくいったためしがない」などと、すべてが同じ結果になると決めつけてしまう。
![]()
結論の飛躍
確かな理由もないのに、深読みをして悲観的・否定的な結論に結びつけてしまう。
![]()
自己関連づけ
何んでもかんでも「自分に関係がある」「自分のせいだ」などと自分を責めてしまう。
このような考え方が根本にあると、ネガティブな自動思考がわき起こりがちになってしまいます。
凝り固まったスキーマに「待った!」
ネガティブな自動思考には、パニック障害・不安障害のときの「予期不安」も含まれます。
「また発作を起こすかも…」「倒れたらどうしよう…」などといった不安感がわき起こってきたら、まずどうしてそう思うのかを考えてみましょう。
-

-
参考自動思考とスキーマ(信念)
続きを見る
「自動思考とスキーマ(信念)」のページでも例を挙げましたが、パニック発作に対する不安感の裏側には、このような考えがあるのではないでしょうか。
![]()
- 以前同じ場所で発作を起こしたから、また起こすだろう
- 発作を起こすことは、みっともないことだ
- 発作を起こしたら、大変な事態になる
- 発作は自分ではどうにもできない など
これらは、前項で挙げた「凝り固まった考え方」におおよそ当てはまっていますよね。
「以前もあったからまた起きるだろう」というのは、主に「一般化し過ぎ」です。過去に起こったことが今後ももれなく起こると思ってしまっているのです。
「みっともない」というのは、「感情的な決めつけ」でもあり「結論の飛躍」でもあるでしょう。本当に発作がみっともないのかと言えば、そんな理由はまったくないのですから。
「大変な事態になる」や「自分ではどうにもできない」というのも同じですね。実際には大変な事態になるわけでもありませんし、自分ではどうにもできないわけでもないのですから、事態を「拡大解釈」し、自分の対処能力を「過小評価」していることになります。
最初に挙げた「LINEの返信がなかなかこない」という例もまた、後者の「ムシされた!」という自動思考が7つのスキーマの影響を受けていることが分かります。
本当に無視されたのかどうかその時点では分からないのだから、やはり結論が飛躍していると言わざるをえません。
ネガティブなスキーマに疑問を持つ
このようなスキーマが見つかったら、「本当にこの考え方は正しいのか?」と自分自身に質問してみましょう。
そして客観的な事実に基づいて、その考え方に反論しましょう。例えばこんなふうに。
発作を起こすのがみっともない? 誰かがそう言ったの? もし立場を入れ替えたとして、自分の周りで誰かが発作を起こしたとしたら、それを「みっともない」と思うだろうか。自分なら思わない。
![]()
発作を起こすのはみっともないとは言えない。
発作は自分ではどうにもできない? 本当に? 呼吸法や漸進的筋弛緩法を練習しているおかげで、少しずつ発作や予期不安をやり過ごせるようになってきてはいないか?
![]()
発作は自分で対処できる。
リラックス法を定期的に練習すれば、もっとスムーズに使えるようになるだろう。
こんなふうに、極端に凝り固まったスキーマに対して疑問を持ち、事実に基づいて反論するのです。

これを習慣づけることで、自分の思考のクセが分かってくるとともに、凝り固まったスキーマがほぐれていきます。
認知行動療法を続けるとネガティブな思考回路が少しずつ改善していくため、ストレスの対処がうまくなります。
疾患から回復した後の再発率が低い理由は、この点が大きいと言えるでしょう。
ネガティブな思考に「待った!」をかけて反論する習慣を、ぜひ身につけていきましょう。